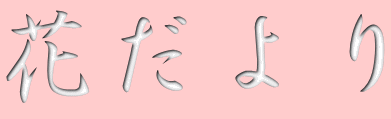 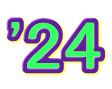 画像をクリックしますと大きい画像が見られます。 掲載されている画像はほとんど無許可で撮影されています。 動植物、建物の所有者の方で、画像の削除をご希望される方は こちらまでご連絡ください。宜しくお願い致します。 削除希望メール '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25 |
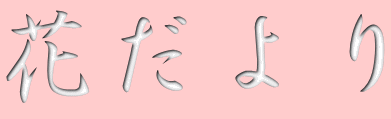 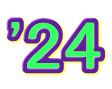 画像をクリックしますと大きい画像が見られます。 掲載されている画像はほとんど無許可で撮影されています。 動植物、建物の所有者の方で、画像の削除をご希望される方は こちらまでご連絡ください。宜しくお願い致します。 削除希望メール '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25 |
| 町内の野良猫が減ったのか散歩していてもあまり見かけません。寂しい限りです。 木瓜と書いてボケ。花期は3~5月ですが今頃咲いたりするのでボケかなと思っていましたが語源は瓜に似ている果実が実るため、木になる瓜で「木瓜(もけ)(もっけ)」と呼ばれ、それが変化してボケになったそうです。 セロシアは和名「ヤリケイトウ」。 ナナミノキは初めて見ました。モチノキ科なのでクロガネモチの実に似てますね。 今年はこれでおしまい。また来年もよろしくお願いします。 12月21・26・他日撮影。 | ||||
|
||||
| えんどう豆かさやえんどうでしょう。 紅葉と鐘楼は永福寺さん。除夜の鐘突くのかな?最近は騒音問題とかで大変なようです。世の中変わりましたね。変わったと云えば郵便ポストも変わりました。可愛くていいですね。町会内の東小松川三郵便局前。 ヒイラギナンテンはヒイラギと南天を掛け合わせた物ではありません。別物です。 オオセンナリはこぼれた種から咲いたようです。開花時は7・8月頃です。寒いのでさすがに丈は伸びません。 我家のヒイラギ、ギザギザがあり、一目でヒイラギと分かります。 12月11・14日撮影。
|
||||
| キチジョウソウは吉祥草、縁起の良い花です。お釈迦様が悟りを開いたときに菩提樹の下にキチジョウソウが広がっていたとか、キチジョウソウに座していたとか云われています。 撮影しているときはヒイラギと思っていたのですが、葉にギザギザが無く調べてみました。木が大きく成長すると異形葉(いけいよう)と云って葉が丸くなるそうです。我家のは鉢植えで大きくならないのでギザギザですが花は少し咲き実も付きます。 12月3・6日撮影。
|
||||
| ツワブキから茶ノ木までは皇居東御苑にて。 三宝柑とギオンボウは日本古来の原種。ギオンボウは干柿にするそうです。 トンビ?は船堀駅の上空を旋回していました。 去年採ってきたギンバイカの実をよく天日干ししてから挽いて粒状にしてスパイスとして使ってみました。味は良いのですが粒が大きくて口に残ります。もう少し挽かないとだめなのかな? フレボディウム?はシダの仲間です。 11月の8日から風邪をひいたようで39度以上の熱が出て10日程臥せっていました。ホームページの更新が出来ずすみませんでした。 10月26日・11月3・19・24日撮影。
|
||||
| 中土手はススキとセイタカアワダチソウがすごいです。その中に混じってヒマワリが今が盛りと咲いています。 ハナミズキの近くにいた、久々に見る大きな蜘蛛です。これがあの有名なジョロウグモです。 10月25・26・30・11月3・4日撮影。
|
||||
| ヨメナかノコンギクかミヤコワスレか分かりません。みんな同じに見えて区別がつきません。 観賞用の唐辛子です。観賞用でも食べられるものもあるそうですがこれは分かりません。 9月28・10月12日撮影。
|
||||
| ナデシコも色々な模様が有ってきれいですね。 ニオイザクラは名前どおり好い匂いがします。 シソは小さな花です。葉も実も食べられますが私は葉が嫌いで食べません。実は醬油だか塩に漬けたのは食べます。 9月28・10月6日撮影。
|
||||
| ギンナンが歩道に落ちて、踏まれて臭い匂いがする季節になりましたね。 黄色いリコリスはショウキズイセンとも云います。 タマサンゴは別名「フユサンゴ」、これから赤い実が生ります。毒が有りますので食べられませんが、花よりも実を観賞するための植物です。 9月14・21日撮影。
|
||||
| 秋分の日に皇居東御苑へ散歩に行きました。暑さ寒さも彼岸までとはよく言ったもので昨日までの暑さが嘘のようです今日は。上皇様が植えた原種の木々に実が生っていました。以前世話をしている人に聞いたら原種なので不味いですよと教えてくれました。最後は尚蔵館に寄り、二十数年振りに名画と再会。 9月22日撮影。
|
||||
| 風船カズラの種、ハート模様です。知ってました? 見かけたら種を調べてください。 桔梗は秋の七草の一つ。 9月14・21日撮影。
|
||||
|
|
||||
| 秋の七草のひとつ、クズが咲き出しました。秋の七草、云えますか? 「萩、尾花、葛、撫子(ナデシコ)、女郎花(オミナエシ)、藤袴(フジバカマ)、桔梗」。散歩した時に探して見てください。 8月31・9月7・10日撮影。
|
||||
| ヤマボウシの実はとても甘くておいしいです。ナツメを食べてみたいのですがよそ様のもので手が出ませんでした。 コムラサキは実がぴっちりと付きますがムラサキシキブはまばらに付きます。 8月15・29・31・9月7日撮影。
|
||||
| 暑い中、涼を求めて目黒自然教育園に行ってきました。自然教育園ですのであまり人の手を加えません。なので5年前の台風で倒れてしまった「大蛇の松」も自然の移り変わりを見てもらうために、そのままにしてあります。散歩道11に倒れる前の画像が有りますのでご覧ください。楽しみにしていたヒグラシのカナカナカナの声が聞こえませんでした。午前中だからかな、カナカナカナ。帰りは一駅歩いて恵比寿ガーデンプレイスに行って、ビールを飲みました。 8月12日撮影。
|
||||
| 緑のキカラスウリの実、しばらくすると黄色くなっていきます。カラスウリは赤くなります。 キササゲの実は長さ30センチぐらいになります。木は高くなるのでお寺や神社で避雷針代わりに植えられ「雷除けの木」と呼ばれているそうです。この木も川越のお寺さんにありました。 ケラトテカは一瞬ゴマかなと思いました。やはりゴマ科でした。 スイレンに似ているのでスイレンボク。 7月27・28・8月4日撮影。
|
||||
| カラスウリは夜の9時ごろ撮影。まだひげが伸びていないので夜明けに撮りに行ったらすぼんでいました。 ワイルドオーツは別名「偽小判」。小判と云えば新紙幣は見ましたか? 私は24日に初めて5000円札を見ました。ちょっとありがたみが有りませんね。 クルクマは観賞用の花で食用にするのはウコンと云います。酒飲みの方は飲んでいるのでは。 7月13・20・21日撮影。
|
||||
| 18日に梅雨明け、水不足が心配ですね。 ミズヒキは小さな花です。名前どおり紅白のかわいい花です。 ハブランサスかゼフィランサスかよく分かりません。 日陰にあるためかまだすぼまないキカラスウリ。次回はカラスウリの画像を載せられそうです。 7月20日撮影。
|
||||
| フロックスは「花魁草」、オミナエシは「女郎花」と書きますが、今では差別的な言い方なのかあまり聞きません。フロックスは白粉の匂い、オミナエシはおしっこ臭いと云うかネットでは蒸れた足の裏のにおいと散々な云われ方です。 月桃と書いて「げっとう」と読みます。三沢あけみさんが歌った「島のブルース」に出てくるサネン花がこれです。 6月30・7月5・8・13日撮影。
|
||||
| レモンマートルを調べましたら葉を乾燥してハーブとして使ったり「抗菌・抗炎症作用」「鎮静・鎮痛作用」「抗酸化作用」など美容や健康に良いそうです。美肌効果・免疫力アップと好い事ばかりです。葉っぱ採ってこようと思います。 ツユクサの花弁は3枚です。青2枚と黄色い雄しべの下の白いのが1枚です。黄色いのが4本と長いのが2本が雄しべです。 蠟細工の様なのでワックスフラワー。 6月30日撮影。
|
||||
| ルコウソウは松葉です。 インパチェンスには距(きょ)と呼ばれるしっぽが付いてます。蜜が入っているそうです。距のあるのは他にカッシア、すみれ、ホウセセンカ、他にもあるのでしょうが私が知っているのはこれくらいです。 ジギタリスは心臓発作を抑える薬に使われています。多量に摂取すると死に至ります。昔、刑事コロンボでジギタリスを使った殺人事件をやっていました。 6月30日撮影。
|
||||
| 日本原産のアジサイ。墨田の花火とかきれいな名が付けられています。何百種類もあるそうです。大きく分けると墨田の花火のような額アジサイと、丸く咲くホンアジサイです。てまり咲きとも呼ばれています。6月21日に梅雨入りしましたが、うっとおしい梅雨時期にきれいに咲いてくれるアジサイを楽しんでください。 6月1・8日撮影。
|
||||
| 6月中旬なのにまだ梅雨入りしませんね。 ブーゲンビリアは白く咲いているのが花で、周りのピンクや赤いのは苞(ほう)と呼ばれ葉が変化したものです。色も変化するみたいです。 アメリカデイゴ、和名「カイコウズ」鹿児島県の県の木です。 オクナセルラタは別名「ミッキーマウスの木」。 6月1・3・5・8撮影。
|
||||
| 9日の日曜日に皇居の花菖蒲を見に行ってきました。花菖蒲の他にも色々な花が咲いています。ヒシバデイゴは少し離れたところからの撮影ですので花の形が分かりませんがカイコウズ(アメリカデイゴ)に似ています。 半夏生は上の方の葉だけが半分ほど白くなります。なので半化粧かと思ったのですが違うようです。 ネジバナは右巻きと左巻きです。 今回は花菖蒲がメインで無く、二十数年振りに見る唐獅子図屛風がお目当てです。三の丸尚蔵館が建て直され、その記念に展示されました。以前は撮影禁止と記憶していましたが今回はなんと撮影OKです。びっくりしました。 ハッピーな一日でした。 6月9日撮影。
|
||||
| 亀戸の新六ノ橋のたもとにあるジャカランダ。世界3大花木、ジャカランダ(紫雲木)、鳳凰木、火炎木のうちの1つだそうです。 ヤセウツボは他の草の根に寄生して栄養をとっています。 アベリアはつぼみです。 オトギリコボウズの実ばかりでしたが一輪だけ咲いていました。 5月30・6月1・8日撮影。
|
||||
| そこら中にはびこっているドクダミ、八重咲なら嫌われ者にはならないでしょうね。 スモークツリー(煙の木)とはぴったりな名です。 ジューンベリーは甘くておいしいです。(女房の感想)
我家のバニーカクタス、今年初めて花が咲きました。 エキザカムと青いバラ、写真撮っている時は気が付かなかったのですが、編集で画像を大きくしたら造花でした。よくできています。 5月17・22・24・25・29日撮影。
|
||||
| 先日、久々に旧古河庭園に行ってきました。きれいにバラを咲かせています。プリンセス・ドゥ・モナコはグレース・ケリーのことです。ドゥヌーブ、バーグマン、若い人はご存じないかもしれませんがこの3人は女優さんです。バラに自分の名が付けられたら嬉しいでしょうね。プリンセス・マサコもあるそうですが分かりませんでした。 5月18日撮影。
|
||||
| 桜よりきれいだと思うサクラウツギ、私だけでしょうか。 白くてもムラサキツユクサです。 スイカズラは金銀花とも呼ばれています。はじめは白、時間がたつと黄色に変わります。箱根ウツギも白から赤に変わります。ニオイバンマツリは紫から白です。 母子草に比べて父子草(チチコグサモドキかも)の色の悪さ、色気が無いから父になったらしいです。 5月5・6・8・11・17日撮影。
|
||||
| フタリシズカ(二人静)からハクウンボクまでは板橋区の赤塚植物園にて。 イスノキの虫こぶにはアブラムシが寄生しており、秋に穴が開いて出ていくそうです。木は算盤の玉に使われています。 頬紅金雀枝は「ほおべにえにしだ」と読みます。 タケノコは親水公園にて。 忘れな草は「勿忘草」と書きます。 5月4・5日撮影。
|
||||
| 大判草は別名「合田草」。 ローズゼラニウムか蚊取り草、花が同じなのでどちらか分かりません。 金魚草はティンカーベルと云う種類。 4月17・29・5月4日撮影。
|
||||
| ハイノキは「灰の木」初めて見ました。 ヒトツバタゴは別名「なんじゃもんじゃの木」。あまり見慣れない立派な木を呼ぶそうです。他に「クスノキ、ニレ、菩提樹」等があります。 色が少し褪せていますがフロックスはシュガースターと云う種類だそうです。アスペルラも初めて見ました。 4月27・29日撮影。
|
||||
| オルレアの写真を撮った時には気が付きませんでしたが画像を大きくしたらヒメマルカツオブシムシがいました。 何もみじか分かりませんが種です。 マツバウンランかと思いましたが姫金魚草でした。 4月17・2026日撮影。
|
||||
| カラタネオガタマはチューインガムのような甘い香りがしますが、香るのは午後からです。撮影したのは午前中でしたので香りませんでした。 マヌカハニーはこのギョリュウバイの原種から採るそうです。 最近、勢力の衰えたナガミヒナゲシですが、あるところには結構群生しています。 クロホウシは花が咲くと寿命が尽きると言いますが本当でしょうか。 4月7・17・20日撮影。
|
||||
| 開き過ぎたチューリップではないと思います。 牡丹、シャクナゲ、藤がもう咲いています。 ムラサキハナナは別名「オオアラセイトウ、諸葛菜(ショカツサイ)、花大根」などと呼ばれています。食べられます。食べられると言えばキンレンカは花まで食べられます。食べたことないので味は分かりませんがあまり美味そうには見えません。 4月3・7・8・13日撮影。
|
||||
| そばを通るだけでも臭いヒサカキ。たくあん食べて一発したような。 白い花が茶人に好まれ、千利休にちなんで利休梅。 3月30・31日撮影。
|
||||
| 3月末になってようやく暖かくなり桜も咲きました。 アオキの花は小さくてきれいに撮れませんでした。 ちょっと汚らしくなりましたがヌカイトナデシコだと思います。 エンドウはスナップエンドウでしょうか。 グランドの花壇は白鷺学校の生徒やしらさぎ野球部の皆さんがきれいにしてくれています。ありがとうございます。 ソテツは種が出来ています。漢字で蘇鉄、木が弱った時に鉄釘を打ち込んだり、根元に鉄くずを施すと蘇生すると云われています。それで蘇鉄です。 3月24・30日撮影。
|
||||
| 今日は3月16日、花の写真を撮りながら歩いているとわきの下に汗をかくほど暖かくなりました。これなら21日に桜が咲くと思いましたが桜の花芽を見るとまだまだのようです。江戸川区は少し気温が低いのでしょうか。でも他の花々は咲き始め、やはり春ですね。 以前は珍しかったレモンですが近頃はあちらこちらで見かけます。 3月10・16日撮影。
|
||||
| タネツケバナのやわらかい若芽、若葉は軽く茹でて水にさらし、おひたし、和え物にするそうです。 もうアケビが咲いています。花はいっぱい咲きますが実が付くのは少ないです。受粉しないのかな? 2月25・3月10日撮影。
|
||||
| 3月2日に小石川植物園へ観梅に行ってきました。お天気は良かったのですが、今年初めての花粉症状が出てしまいました。 色々な花が咲き出し春を感じます。 ムクロジの実の種は昔、羽付きの頭、皮は洗濯に使っていました。 温室にはラン系や珍しい花が咲いています。 楽しいひと時でした。
|
||||
|
||||
| 色違いの初恋草、横文字でレケナウルディア、和名の方がとても覚えやすいです。 エリカはベスティタシャイニングブライトと云う種類だそうですがエリカとだけ覚えてください。 梅の名が付いていますが梅の仲間ではありません。梅の花に似ているのでオウバイ。 水仙はペーパーホワイトと云う種類です。 2月15・17・18日撮影。
|
||||
| 2月11日に後楽園プリズムホールで開催されているらん展に行ってきました。コロナをあまり恐れなくなったのか、すごい人出でした。出品者の皆さん、きれいに咲かせお見事です。ありがとうございます。
|
||||
| 今年は暖冬なのでしょうか。まだ一度も氷が張りません。もう張らないでしょう。 台湾椿、雨に濡れて花びらが少し透けています。 イヌホオズキはナスやホオズキに似ていますが役に立たないことからバカナスとも呼ばれています。 1月21・23・28・2月3日撮影。
|
||||
| 早咲きの梅を見に小石川後楽園に行ってきました。花は少ないですが梅の香りがします。 唐門は空襲で焼けてしまいましたが、昔の写真を基に令和2年に復元されました。唐門は、屋敷の書院から内庭を通り、後楽園に入る正式な入口です。普段は閉まっていますが、特別な催しものがある時は通行できるそうです。のんびり、楽しかったです。 1月28日撮影。
|
||||
| 我家の万年青(オモト)、今頃になると実が出来たかなと見るのですが、花が咲いているのを見たことが無いと気が付きました。今年は必ず花を掲載します。 梅が咲き出したので観梅に行ってきます。 1月27日撮影。
|
||||
| 今年もよろしくお願いします。1月13日に積もりませんでしたが雪が降りましたね。雷もゴロゴロピカピカ凄かったですね。 クリスマスホーリーは西洋ヒイラギ、実は万両に似ています。 ロウバイは必ず匂いをかいでください。必ずああ好い匂いと云いますよ。 ツルニチニチソウ、ユキヤナギ、オオセンナリは戻り咲きです。 グリーンネックレスは球状ですがこれは三日月です。花はどちらも同じように思います。 1月6・13日撮影。 |